床・建具を知っておく
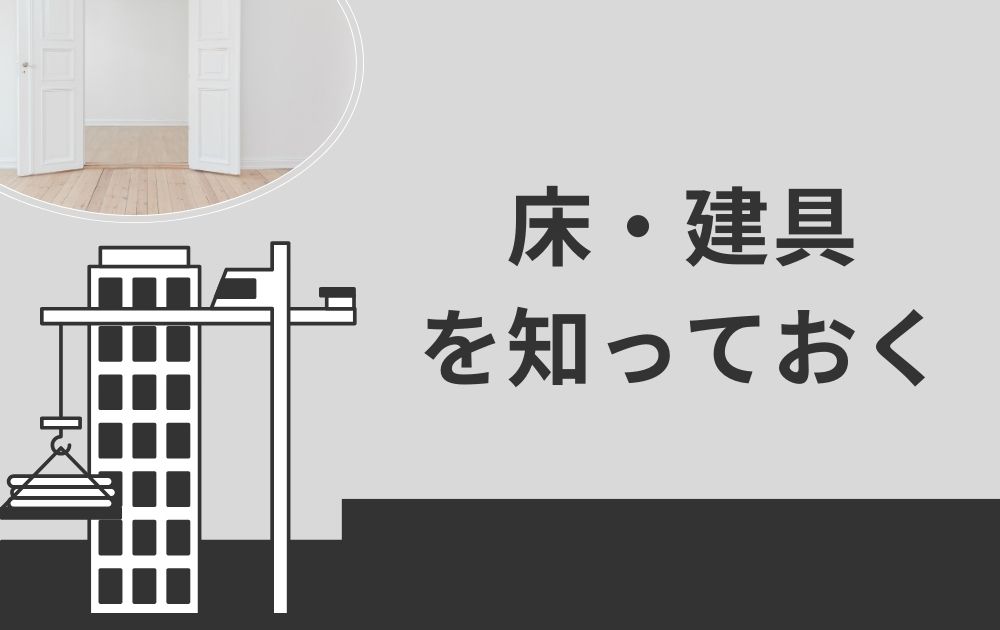
床・建具とは?
床・建具とはフローリングやドアの事です。収納扉の折戸も建具に入ります。建具に関しては国内主要ブランドが固定化されている傾向がありますので、投資物件においては建具は主要な国内メーカーのものを選びます。
床に関してはフローリングにすべきか、フロアタイルにすべきかは区分所有であればマンションの規約もありますので、そちらに従う方向で一番コストが安く済むものを選択します。無垢材を使用したリノベーションもありますが、あれは賃貸物件ではおすすめしません。
無垢材は張り替えた時は良いですが、2年間の賃貸借契約期間中に退去して、次の入居者が住む頃には既に変色しています。その変色が味があって良いという人もいますが、不潔感を感じる人の方が多いからです。
また、材料費も施工費も無垢材は高くつきますので、投資対効果を考えるとあまりおすすめできるアイテムではありません。
フローリングについて
柔らかいフローリング?硬いフローリング?
フローリングの素材には大きく2種類あります。防音用の吸音材が入っているL45(エルヨンジュウゴ)またはLL40といわれる床材が一つ。もう一つは通常の硬いフローリング材を使用するケースです。ただし、L45の床材を使用しなくても最近は吸音材の入ったフローリング下の下地材(置床支持脚)を使用することで同等の吸音効果を出して対応するケースもあります。これは二重床と言われる施工方法です。
特に一時期よく使用されたLL45と言われるさらに吸音効果の高い床材は踏み込んだ際に柔らかい感触が強くあり、その感触が苦手なお客様が多くいました。そのため、同等の吸音効果でそういった柔らかい感触の無い二重床を採用するお客様が増えています。また、フローリングの素材自体も色々なものがあります。無垢材を使用した高級なものから、表面が木目のように見えて実は印刷のシートが張られているフローリング材もあります。
木材の種類自体もウォルナット、オーク、パイン等多くの種類があります。その中からどういった床材を選ぶべきかを検討していきましょう。
無垢材について
リノベーションにおいてよく提案を希望される床材に無垢材があります。無垢材は確かに仕上がりはとてもきれいで自然感があり人気があります。実際に無垢材自体はとても良い品質の床材であることが多いです。しかし、メンテナンスという観点からいうと必ずしも無垢材が良いとは言い切れません。
無垢材は素材によってはワイン等の染みがつきやすい水分をこぼすと汚れがおちません。削って落ちる事もありますが、コーティングされていないため、樹脂の目に染みが入りやすく無垢材自体が染まってしまうからです。また、無垢材のフロアを1枚ずつ貼るため目地ができやすくそこにゴミが詰まるというデメリットもあります。
窓際等で湿気が多い場所の無垢材が変色してしまう事例もあるため、長期に渡ってメンテナンスをする覚悟もある程度視野に入れて導入されることをお勧めします。試しにネット検索で「無垢材 汚れ」と検索してみると良いかと思います。また、床材に傷が入った際に「リペア」という修復工事をして床の傷を隠すメンテナンス方法があるのですが、無垢材に関してはこの「リペア」での修復が難しいケースが多いです。
ただし、それでも「無垢材はとてもいい床材」です。どちらの立場なんだ?と思われるかもしれませんがモノがいいという事だけは断言できます。そしてやはり無垢材で仕上がったばかりのリノベーションされた部屋は最高に美しいです。
色のバリエーション
フローリングの硬軟や素材をカタログやサンプル等である程度決めた後に、最後は色の選定があります。色に関しても多くの種類がありますが、フローリングは自然素材が多いため、他のキッチンやユニットバス程多様な色があるわけではありません。
そのため、お客様の中である程度好きな色や建具の色が決まっていれば迷わず決められるケースが多いです。好きな色でいくべきか、お部屋全体のトーンと合わせたいん場合は建具と同じ色にすべきか。そのどちらかで迷われるケースが多いです。
フローリングのグレード別のカタログの中で、白系であれば3種類、ブラウン系であれば3種類、ベージュ系であれば3種類といったそれほど多くの選択肢も無いケースが多いため大まかに色が決まればそこから先の選択ではあまり悩まれないのかもしれません。
ただし、小さなフローリングのサンプルや写真だけではわからないかもしれませんので、もしもっと大きなサンプルを見たい場合はメーカーのショールームに行くことをお勧めします。また、一般的によく使われるフローリングであればリノベ工事会社の施工事例写真も豊富にあるケースが多いため施工事例を多く見せてもらうのも良いかと思います。
床材も価格幅が大きい
フローリングもメーカーごとにいくつかのブランドを持っている事があります。特に大建工業や朝日ウッドテック等のフローリングに力を入れているメーカーであれば複数のブランドを展開しています。当然ですが、そのブランドごとにフローリングの単価も異なります。
「フローリングなんて高くてもそんなに変わらないんじゃないの?」と思われるかもしれませんが、試しに高級なフローリングのカタログをご覧頂ければわかりますが、見た目からしてとてもいいものが多いです。
また、工事会社に見積の際にどれくらいのレベルのフローリングを使いたいのかをあらかじめ伝えておけると正確な見積が出やすいです。フローリング自体はとても広いスペースを張り替えます。1箱で1坪(約3.3㎡)の床材が入っていますので、60㎡のマンションになると20箱近く仕入れます。そのため、1箱の単価が高いと×20倍になります。予算にも注意して適切なフローリング材を選択していきましょう。
投資物件はフロアタイルも積極的に検討する
一棟収益の所有を検討する方や、既存床への上張りを検討する場合はフロアタイルの使用をおすすめします。フロアタイルとはサンゲツが製造している樹脂製の床材です。上張りが可能な薄さと強い耐久性があります。また、見た目がフローリングにそっくりなためデザイン性も保てます。
最近では敢えて、木目を選ばずにタイル調の店舗用床材を選択されるケースもあります。何よりフローリングよりもコストが半分程度に済むのが魅力です。
https://www.sangetsu.co.jp/newproduct/floortile21/
建具について
建具(タテグ)の種類
建具(タテグ)とはドアや収納の扉の事です。下駄箱も建具として考えます。建具の色や形で部屋の印象がかなり変わってきます。ドアの色や形ってそんなに多く思い浮かばないかもしれませんが、実は非常に多くの種類があります。
Panasonicのベリティスという建具のシリーズのカタログは電話張くらいのサイズがあります。シンプルなようで実は奥が深いのが建具です。またリノベ会社の施工管理をする現場監督が一番発注にナーバスになるのも建具です。
https://sumai.panasonic.jp/interior/veritis/
少しでもサイズや形を間違えて誤発注すると現場では使い物になりません。基本的には返品も受け入れてくれないため、お客様はもちろんのこと、現場の大工さんとも入念に打合せをしてから発注を掛けます。
どんな種類があるのか?
建具には室内の入り口に使う「開き戸」や「引戸」がまずあります。「開き戸」の中にも中央にガラスが入っているもの、鍵のついているもの、サイズもいくつかあり多岐に渡ります。また、「引戸」の場合は戸袋という引戸が隠れる場所が必要なものと必要ないもの等複数あります。
また、室内に入って収納の扉も建具です。収納の場合は一般的には「折戸」と言われる二つに折り畳む形式の扉が複数枚着いた収納扉を使用します。ですが、ウォークインクローゼットの場合は引戸を入り口に使うことも多くあります。
室内間を間仕切る建具もあります。「連動引き戸」「間仕切り戸」等と呼ばれる建具で例えばリビングと洋室の境目に設置して、間仕切りとして使う事もあれば、間仕切りを収納して広いリビングとしても使えるというメリットもあります。
最後に下駄箱ですが、下駄箱も中央で上下にセパレートしているものと、一体型のものと種類があります。また鏡がついているものや複数の下駄箱を連結させて大きな下駄箱として使用できるタイプものと以外な程多くの種類があります。
全部同じ色の方がいいいのか?
建具の色を決める際にはどのような考えで決めるのがいいのか?悩まれる事も多いと思います。一番は最初にリノベのイメージを決めた際になんとなく好きだなと思っていた色を優先させた方がいいかと思います。
おススメの色はありますか?というご質問も多く頂きますので、その際はコーディネーターからご提案をする事もあります。また、よく使用される色は「白系」が多いです。あるいは床の色に合わせて全体を統一したトーンにされるお客様もいらっしゃいます。
また、全ての建具が同じ色である必要もありません。リビングの入り口のドアだけは違うテイストにしようとか。寝室の収納扉は少し濃い色を使おうとか、ご自身で住まわれる家であれば常識を考慮せずに複数の色の建具を使ってみるというのもありかもしれません。

