アパートローンの現状(2023年後半)
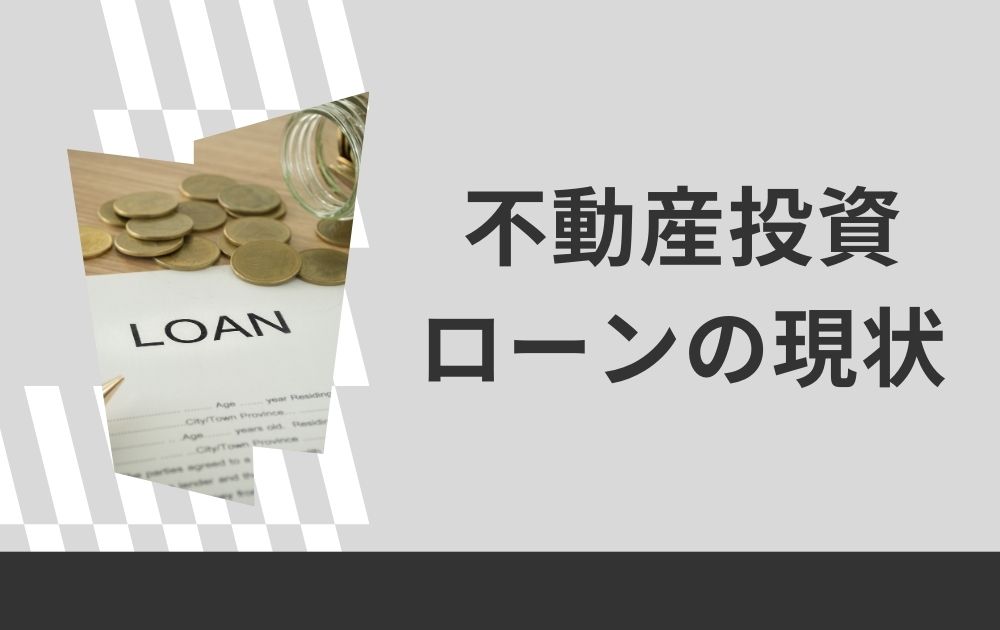
不動産投資ローンの現状
積極融資姿勢ではない状況は続いているが・・・。
2017年前後から相続税の税制改正により不動産投資が過熱化し不動産投資ローンの件数も右肩上がりに増えました。その後、かぼちゃの馬車事件やTATERU等の不動産投資に絡む不正融資により、金融庁から各金融機関への引き締めが入りました。その流れもあり不動産投資への融資実行額は減少し、融資審査も厳しくなっています。
上記の流れから、2018年頃から個人投資家が不動産投資に絡む融資を受けることが難しくなったといわれており、2023年においても引き続き同じ状況が続いています。
しかし金融機関も利息を稼がないといけない立場であり、不動産と並ぶ大口融資先である通常の企業融資が昨今はコロナ渦中のゼロゼロ融資の焦げ付き等で貸し渋り傾向にあります。結果として、最近では、企業融資も減少傾向になってしまうことから、金融機関は改めて収益不動産を有望な融資先と見ており、以前に比べると、やや融資に前向きになっている傾向があります。
「かぼちゃの馬車」事件をはじめとする地方銀行の不正融資や、不動産投資の過熱による供給過多などを原因に、今アパートローンの動向には変化が見られています。
賃貸マンションやアパート投資に対する、ここ数年の融資の動向を理解しておきましょう。
一棟マンションへの融資引き締め
一棟収益の融資は当然融資額も高額になり、都心では億単位の取り引きとなることが多いです。以前から、金融庁が一棟向け融資に対するリスクを強く懸念しており、近年一棟収益の融資は非常に厳しくなっています。
そのため自己資金が少ない場合、一棟マンション・アパートで融資を受けられる可能性は低いといえるでしょう。そこに関してはあまり抜け道は無いと思っておいた方が良いです。
築古物件への融資は難易度が高い
物件の構造により法的に耐用年数が決まっており、木造は22年、RC造は47年となります。以前は、法定耐用年数を超えた築古物件であっても、現実的な耐用年数である、経済耐用年数を考慮し融資をしてくれる金融機関もありました。ですが、最近では、築古物件で融資を受けることは非常に難しくなったといわれています。
一部のノンバンクなどでは、築古物件への融資が取り扱われているケースもあります。しかし、設定される金利が高い場合もあるため、注意が必要でしょう。
アパートローン利用時の注意点
ではアパートローンを利用する際、どのような点に注意するべきか整理します。
頭金を用意できるか?
基本的に不動産投資においては以前のようなフルローンでの融資設定は難しくなっています。事実、ほとんどの案件で融資審査が厳格化されて以降、金融機関が頭金を求める傾向があります。
アパートローンの融資審査を有利に進めるためには、10%前後は頭金が必要になる想定で準備をしておいた方が審査を進めやすいです。
確かに以前はほとんど自己資金無しでフルレバレッジでローンを組むことができました。ですが、恐らくその時代に戻る事はないと思っておいた方がいいでしょう。金融庁は一度規制を作るとそこからは緩める事は基本的にはしません。
特に投資物件のフルローンに関しては極端すぎる融資姿勢だったので、安易に引き締めを緩める事はできないと考えます。
自己資金が少ない方は、その少ない自己資金を頭金にして購入できる物件から少しずつ資産を増やしていく方が近道になります。
物件の収益性シミュレーション
アパートローンの融資申請の前に物件の収益シミュレーションをしっかり行っておくことが重要です。家賃収入とローンの返済額だけではなく、原状回復費や空き室リスク等も加味してシミュレーションをしておくことが必要です。
また、そのシミュレーションが絵空事ではなく、できるだけ現実的で且つ信頼に足るものである必要があります。特にデータや数値を基にした現実的な事業計画書を金融機関に提出する必要があります。それにより、金融機関に与える印象も変わります。
返済計画の妥当性
返済比率とは、不動産からの賃料収入に対してローン返済額が占める割合を表したものです。
年間のローン返済額が600万円、得られる不動産収入が1,000万円の場合、
600万円÷1,000万円×100=60
で、返済比率は60%と計算できます。
アパートローンの返済比率は、50%程度に抑えておくことが望ましいとされています。要するに返済から残る手残りが家賃収入の計画の半分程度は手元に残るのがベストです。
そこから現実的には空き室率や税金や原状回復工事等の費用が発生します。急遽発生する費用にも安心して対応することができ、自己資金からの持ち出しを避けることができるラインが50%と想定されています。
これを実現するためにはある程度の耐用年数残があり、長期の融資を組める事が重要になります。
コロナ明けでの融資状況の変化
コロナ渦が明け、金融機関のアパートローンへの投資姿勢はどのように変化しているのでしょうか。
企業融資に積極的になれない理由
コロナ禍において、ゼロゼロ融資等の大幅な金融緩和に金融機関は協力してきました。その跳ね返りがあり、焦げ付き始めたゼロゼロ融資を中心とした不良債権への懸念が高まってきました。
そのため、企業の通常の運転資金の貸し出し等に関しては若干の貸し渋り姿勢が見えます。ですが、その反面融資先を安定的に確保して利息を稼がないといけない金融機関としての立場もあります。
その点では不動産への融資というのは大口な融資先として金融機関も見逃せない分野になります。事実、不動産会社向けの短期のプロジェクト融資に関しては積極的に応じている金融機関が多いです。
とはいえ、一般の不動産投資家向けのアパートローンは長期での融資となるため、かなり慎重に取り組んでいる金融機関が多いのが現状です。その点は以前よりはマシになったけど、そこまで積極的な状況には戻っていないというくらいの表現が正確かと思います。
アパートローン貸し出し条件が極端に楽になる事は恐らくない
恐らく金融機関の都合で考えるとアパートローンは積極的に取り組みたいけども、金融庁の手前安易には手を広げられないというのが正直な所かと思います。実際、カボチャの馬車のような社会問題化する事案があった以上は金融庁も監督官庁として規制の手を緩めるわけにはいかないという立場も理解ができます。
そのため、今の状況から極端によくなる事が無い前提で投資計画を考える方が現実的です。例えば自己資金が少ないのであれば地方の築古物件を現金で購入して少しずつ実績を作るとか、自己資金の頭金の範囲で借りれる金額内の物件で実績を積むのが現実的といえます。

